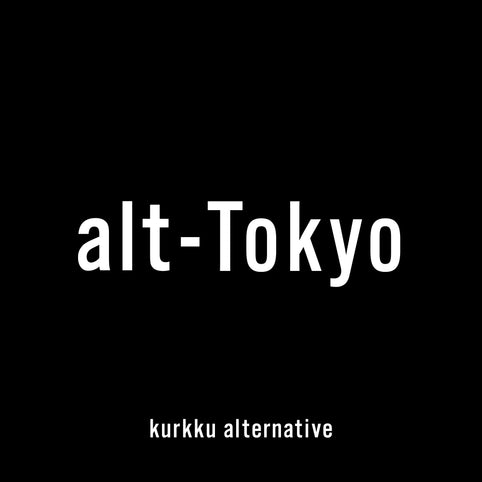豊嶋 秀樹
1971年大阪生まれ。サンフランシスコ・アート・インスティテュートを卒業。チェルシー・カレッジ・オブ・アート・デザイン修了。大阪を拠点にクリエイティブ活動を展開するgrafの設立メンバーの一人。2009年よりgm projectsのメンバーとして主にアート分野で、キュレーション、空間構成、ワークショップなど幅広いアプローチでジャンル横断的に活動。2006年、奈良美智とyoshitomo nara + graf「AtoZ」を共同企画・制作。2010年、三沢厚彦+豊嶋秀樹としてあいちトリエンナーレに参加。2011年、「押忍!手芸部と豊嶋秀樹」として金沢21世紀美術館で個展などのコラボレーションも多い。「マンガ新次元」展(2012年 / 水戸芸術館より韓国、ベトナム、フィリピンへ巡回)、「KITA!!: Japanese Artists Meet Indonesia」(2008年 / インドネシア)。「ホーリー・マウンテンズ」(2006年 / 札幌・モエレ沼公園)、「Reborn-Art Festival」(2019 / 石巻市)など、展覧会や芸術祭のキュレーションや空間構成を担当。
高尾山に登られたことをきっかけに登山を始め、ULハイキング、これはウルトラライトハイキングですね、のスタイルに傾倒。近年は山をテーマとする活動を多く手掛け、九州を中心としたハイカーコミュニティ「HAPPY HIKERS」の運営や、ニセコの複合施設「Camp&Go」のクリエイティブ・ディレクション、アウトドアブランド「山と道」のイベント企画なども行っている。
編集著書に「岩木遠足 人と生活をめぐる、26人のストーリー」。最近はもっぱらサーフィンとスキーに入れ込んでいて、福岡と真狩村に在住している。
instagram : @hidekichi.kngk
Key Words:
サンフランシスコ・アート・インスティテュート / San Francisco Art Institute, チェルシー・カレッジ・オブ・アート・デザイン, graf, 奈良美智+graf AtoZ, 奈良美智, 三沢厚彦, あいちトリエンナーレ, 押忍!手芸部, 金沢21世紀美術館, KITA!!: Japanese Artists Meet Indonesia, Reborn-Art Festival, ハッピーハイカーズ / HAPPY HIKERS, U.L.ハイキング(ウルトラライトハイキング), ホーリー・マウンテンズ, モエレ沼公園, 山と道, Camp&Go, 岩木遠足, kurkku, ap bank, ロングトレイル, レイ・ジャーディン, 槍ヶ岳, テレマークスキー, テレマルク県, バックカントリー, アルペンスキー, パラレルワールド, 高梨 穣,ラタトゥイユ , Quality of Life (QOL), Odakyu OX, 国立民族博物館, ブリコラージュ, エンジニアリング, ハッピーハイカーズ法華院ギャザリング, くじゅう(連山), ティク・ナット・ハン, 羊蹄山, 真狩村
エピソードを読む:
[江良]
本日のalt-Tokyoはゲストに豊嶋秀樹さんをお招きしております。どうぞよろしくお願いします。
[豊嶋]
お願いします。
[江良]
はい。じゃあまず豊嶋さんのプロフィールを僕の方から紹介させていただきます。
1971年大阪生まれ。サンフランシスコのサンフランシスコ・アート・インスティテュートを卒業。チェルシー・カレッジ・オブ・アート・デザイン修了。大阪を拠点にクリエイティブ活動を展開するgrafの設立メンバーのお一人で、2009年よりgm projectsのメンバーとして主にアート分野で、キュレーション、空間構成、ワークショップなど幅広いアプローチでジャンル横断的にご活動されます。奈良美智さんとyoshitomo nara + graf「AtoZ」を共同企画・制作、これは2006年ですね。
2010年に三沢厚彦さんと+豊嶋秀樹としてあいちトリエンナーレに参加。
「押忍!手芸部と豊嶋秀樹」として金沢21世紀美術館で個展、これは2011年、などのコラボレーションも数多くやられております。あと「マンガ新次元展」、これは水戸美術館ですね、(水戸美術館)より韓国、ベトナム、フィリピンへ巡回、2012年。「KITA!!: Japanese Artists Meet Indonesia」、これは2008年インドネシアで。あとは「ホーリー・マウンテンズ」2006年、札幌・モエレ沼公園。「Reborn-Art Festival」、これは2019年から20年、石巻にて。など、展覧会や芸術祭のキュレーションを数多く、空間構成も含めて数多くご担当されています。
で、高尾山に登られたことをきっかけに、登山を始められて、ULハイキング、これはウルトラライトハイキングですね、のスタイルに傾倒。
近年は山をテーマとする活動を多く手掛けられて、九州を中心としたハイカーコミュニティ「HAPPY HIKERS」の運営や、ニセコの複合施設「Camp&Go」のクリエイティブ・ディレクション、アウトドアブランド「山と道」のイベント企画なども行っておられます。
編集著書に「岩木遠足 人と生活をめぐる、26人のストーリー」があります。最近はもっぱらサーフィンとスキーに入れ込まれていて、福岡と真狩村に在住されています。はい。
[豊嶋]
はい。謎な感じですね。
[江良]
そうですね。豊嶋さんは、僕がkurkku、僕は2005年の12月に入社するんですけど、その12月、kurkkuが開く直前になるんですけど、その前ですよね、最初にap bankができて、kurkkuが立ち上がるところで、豊嶋さんがだいぶ活躍というかね、存在が大きくなったんだけども、僕が入った時には他のことが忙しくて、いなくなっていて、豊嶋さんの名前っていうかね、豊嶋さんっていう人がいてみたいな、そういうところでずっと名前を聞いてて、だから、僕にとっては先輩っていうようなイメージがあって、その後2019年に先ほどもプロフィールにありましたけど、Reborn-Art Festivalでキュレーションをお願いしてっていうところで、初めて一緒にさせていただくんですけど、今日は北海道の真狩の豊嶋さんのご自宅にお伺いしております。この羊蹄山がすごい綺麗に見える本当の山の麓に、これセルフビルドと言っていいですかね?
(豊嶋邸と羊蹄山)
[豊嶋]
まあそうですね、仲間と一緒に。
[江良]
仲間と一緒にお家を建てられて、ここと福岡と今二拠点っていう形になるんですかね?
[豊嶋]
そうですね。
[江良]
じゃあちょっと豊嶋さんのこのプロフィール、どういうお仕事かというところなんですけど、でも今豊嶋さんって何屋さんっていうか、アートから入られてきて、今、山のこととか、非常に幅広い、僕にとってはすごい自由な形でいろいろなことを越境されてお仕事をされているのだと思うんですけど、何屋っていうラベルを貼りたいというよりも、何かどういうようなことで仕事を選んだり、もしくは出会ったり、巡り会ったりっていうと、何かその中で自分で大切にされていることが、こういうことが軸になっているとか、そういったものがあれば教えていただきたいんですけども。
[豊嶋]
はい。そうですね。もともとずっと自分もさっきのプロフィールで言ってくださったみたいに、美大を卒業して、それも割とちゃんと行った学校って言ったら変ですけど、アメリカの美大に行ったりとか、その後日本に帰ってきてしばらくして、30歳の時にロンドンの大学院に行ったりとかして、割とがっつりアート、アートみたいな感じでやってきてたんですけども、その後も仲間と一緒にgrafっていうクリエイティブチームみたいなのの創設に関わったりしながら、僕としては同じことだったんですけれども、割とアーティスト寄りに、例えば奈良さんと一緒に制作して作品を作っていくような仕事と、それからもうちょっと展覧会自体を企画していくような、そういうキュレーターとしての仕事みたいなのと、あとは展示のデザインとか、作品がもう結構空間的に広がっていくような場合とか、そういう風になった場合は、空間構成っていう言い方を自分もしてたんですけれども、そういう作品というよりは展示に近いようなアプローチで展示、空間を作っていくとか、そういうものも結構やってきてたんですが、でも振り返ってみるとですけど、最近あんまりそういうのは、言われたら、頼まれたり話いただけたら、もちろんやったりすることがあるんですけど、一時期ほど忙しくしないように心がけておりまして。ていうのが、アート自体は今でも大好きだし、いろんな展覧会を見に行ったりとかもするんですけれども、学生時代から自分がアートっていうものの中でテーマにしてきたのが、アート&ライフっていうようなエリアっていうか、アートとライフ、生活とかがどういう風に相互関係を持てるのかとか、生活の中でアートみたいなものを見つけていくとか、逆に生活をテーマにしたアート作品を作っていくとか、そういうことに自分ずっと興味があったんですけれども、ある時点からそれがより生活にシフトしていったみたいなところがあって、それの大きな機会になったのが、ウルトラライトハイキングって呼ばれる、登山のようなハイキングのスタイルなんですけど、それの影響も多かったなと今は振り返るんですが。
[江良]
そのウルトラライトハイキングっていうのはどういう?
[豊嶋]
ウルトラライトハイキングっていうのは、もともとアメリカのロングトレイルって最近よく行かれている人も何千キロもあるような、そのハイキングルート、その中には山の頂上に行くこともあるんですけれども、より長い距離を歩こうみたいな感じなので、割とこの水平思考なものだと思うんですけれども、そこを歩くために重い荷物を背負っていくんじゃなくて、極力軽い方がいいに決まっているよねっていうことで、ものすごくテントとかも重いものじゃなくて、簡易的なターブみたいなものだけで行こうとか、山ご飯とかは降りてから楽しめばいいから、栄養補給を割と重視して、軽量化された食事でいいんじゃないかとか、必要最低限とか必要十分なものだけで行けば、意外と荷物これだけ軽くなるねっていうのがあって、そういうのを提唱したレイ・ジャーディンさんっていう方がいるんですけれども、その考えがロングトレイルハイカーの方々に結構広く受け入れられるとともに、日本でもこの15年ぐらいですかね、日本にもその考え方が入ってくるようになって、最初は本当にそんなんで山行って安全とか大丈夫なのか、みたいな感じのところがあったんですけれども、今かなり広く普及してるし、従来型の登山の道具自体もどんどん軽くなってきてるんで、15年前に20年前と比べたら全体がウルトラライト化してると思うんですけれども。
(自作のタープ)
[江良]
それは豊嶋さんのアートとアート&ライフの考え方で生活の方にグッとちょっとシフトしたというか、重心が移ったのとはどういう影響だったんですか?
[豊嶋]
それはね、ウルトラライトハイキングっていうものを、一つのメソッドみたいなのの中に、持っているザックの中に入っているアイテムをすべてこと細かに重さを量って、それをリスト化して、そのリストを見ながら、この道具は果たして本当に必要なのかっていうところとか、重複しているものもあるんじゃないかとか、そういう見直しをやっていきつつ、重いなと思うものは軽いものに変えてみたりとかしていって、そういう漠然と荷物をザックに突っ込んで持っていくとか、不安だからこれもいるかなとかってどんどん入れていくっていうことじゃなくて、本当に必要なものだけを極力軽いもので、自分の持ち物をちゃんと自分で認識するっていう、そういう作業があるんですけど、それがやっぱりでかくて。それってハイキングの一つの方法として提唱されているけれども、普通の暮らしの中の話にもすぐ置き換えられるなというふうに自分は思って、断捨離とかそういう言葉もありますけど、僕たちって生活していても、ほとんど使っていないものとかもいっぱいある中で暮らしてたりすると思うんですけど、なんか東京に住んでた時から15年前ぐらいに福岡に引っ越したんですけど、そのタイミングで重なって、本当に仕事が忙しかった時期があったので、そういうんじゃない暮らしがしたいっていうふうに急に思ったっていうのと、登山が始まったっていうシンクロしたという。
(破れたタープで作った自作ザック)
[江良]
シンクロしたっていう。
[豊嶋]
でも、それまで全然山登りとかもしなかった人が行って、これはすごいみたいな、そういう自然に触れたということのインパクトと、そのULハイキングっていう方法のインパクトが相まって、それで引っ越しっていうタイミングがあったので、こんなにたくさん物いらないよね、みたいなことから始まり。その時に、東京では絶対にあり得なかったと思うんですけど、福岡に行った時にね、家探しをしたんですよ。そしたら、また賃貸住宅で、家賃払い続けないといけないのかって、あれ結構毎月毎月って大変だなって、東京の時ずっと思ってたんですけど、福岡に行ったら、ある不動産屋さんで、出されたファイルに、なんとかマンション265万円とか、なんとか団地、なんか340万円とか書いてるようなのがいっぱい入ってるファイルがあって、「あれ、すみません、この340何万円みたいなのって、これなんなんですか?」って言ったら、「すみません、売買物件のファイルが混ざってました」って言うんですけど、僕みたいなフリーランスとかだと、なかなかローンとか組みにくいんですけれども、「ちょっと待ってください」って、「この何百万円、200万とか300万って、キャッシュで用意したら、これ買えるって話ですか?」って聞いたら、「それはもちろんですよ、いっぱいありますよ」って、ガーッて見せてくれて、それで見てたら、東京とも全然、多分前に1がついても、まだ東京じゃ無理ですみたいなね、今なんて特に。どんどん値上がりしてると思うんですけど、あれこれ買っちゃったら家賃なくなるわっていうふうにひらめき、で、もう現金かき集めて、福岡の中央区の端っこの方に、もともと公団みたいな団地の、築30年くらいだったんですけど、まあ、なんか水周りとかきれいだったんで、これ買って自分でリノベーションしようとかいう感じで、そこを購入して、リノベーションして、住んだんですけど、そのことによってやっぱり家賃がなくなるってのと、駐車場もすごい安いんですね、福岡とかまだ。なので、もう絶対に揺るがなかった固定費っていう部分が、ガクッと下がったので。で、東京行った時ってなんか、ほんとちっちゃいとこに住んでましたけど、家賃15万の、車庫が25000円みたいな感じで、20万近いお金が、毎月毎月毎月毎月、年間240万みたいなのは、家賃として毎年必要で、それをフリーランスのクリエイティブ業みたいなのを、アートの世界みたいなのでやっていって、それを稼いでいくって結構大変。240万円支払おうと思ったら、利益が240万ないと、だから仕事的に言うと、その倍とか3倍くらいの仕事をしないと、残らないんですよね。ってことは、500万とか600万とか700万とか、は稼いだ分の全部家賃に消えるみたいな。それが福岡行って無くなったってなったら、年間700万くらい稼がなくなる、よくなったって、もう仕事しなくていいってことなんじゃないか、みたいな気分になるくらいの、やっぱりインパクトがありましたね。
そこから、必要経費って、もう一回全部見直してみようよ、みたいなので、妻と一緒に、電気はどこが契約するといいのかなとか、スマホの契約これでいいのかなとか、これはもう、このやつやめてもいいんじゃないとか、いろんな保険とかも見直したりとか、いろいろグーっと圧縮したら、家賃なくなったんで、さっき言ったのが一番大きかったんですけど、2人で20万円あったら、意外といい感じで暮らしつつ、月3万円くらいは貯金できるねって話だったんですよ。だから実際的には17万円くらいで、十分暮らせて、で、3万円はバッファーというか、残ったら貯金できるね、みたいな感じで、思って、そういう家計費をもう一回見直したんですよ。
[江良]
なるほど。
[豊嶋]
それは、今回の話の核心にもつながっていくんですけど、その時に、決して我慢して、我慢して、節約してっていうよりかは、これだけあったら満足できるね、幸せと思えるねっていう金額をリスト化していったんで、これは幸せの見積書っていう言葉で表現できるなとか思って。そういうことって、普段なかなか、僕は全然やってこなかったし、使ったことをどんだけ毎月使ったかなっていうのは考えるんですけど、それを自分なりに予算化して、これだけあれば、一応満足できる暮らしができるっていうのが見えれば、まあ言えばそれを稼げばいいっていう話になるんで、じゃあ一体どれだけの仕事をしないといけないのか。フリーランスの場合はね、いくつの仕事をしなければいけないのかとか、勤められてても、給料がいくらのところでいいんだとか、もっと給料が高いところにどんどん行かないといけないとかっていうよりかは、これだけあればいいんだっていうのを、具体的な数字として理解できたっていうのは、ウルトラライトハイキングの中での方法論をライフに一回応用してみたら、「わっ!20万で行けるの?2人で」みたいな話で、だから今うちはね、10万ずつ払うってことにしてて。
[江良]
お互い、奥様と。
[豊嶋]
だからそれ以外はもうご自由にどうぞみたいなやり方にしてて、なんですけど。
[江良]
じゃあ、本当に最初展覧会とか作品とかそういったものを、いわゆるクリエーション、作ってるっていうところから、豊嶋さんの人生自体というか、生き方みたいなところを、そういう幸せの家計簿みたいなところを作って、ちゃんと見て、組み立てていくというか。時間もできたから、じゃあそのできた時間で登山もやれるよねとか、そういう生き方を自分で再構成というの、構築していくみたいな、そういうアートというか、そんなような捉え方であってます?
[豊嶋]
うん、なんかまあ、そうですね。なんかこう、アートみたいなものが、美術館の中でとか、額縁の中でとか、台座の上に置かれてとか、そういうものだけじゃなくて、なんかアートを見てハッとしたりとか、おーって思えたりとかっていうことの、その見る力とか感じ取る力を持って人生を見てみれば、めちゃくちゃ面白いこといっぱいあるなって思えるようになってしまい、だから、作品っていう格好付けをして何かこう、ものを作らなくても、今日のお昼ご飯でチャーハン作ろうみたいなのを、めっちゃこう自分なりに、こうやったら美味しいんじゃないかとか、こうやったらうまくいくんじゃないかとか、って言ってチャーハンを作ることで、結構そこに自分のエネルギーというか、なんかこう興奮というか、なんか手応えみたいなのと、それを一緒にしかも食べたりとかして、共有も他の人とできたりするようなのが、なんか本当にアートとは呼ばれないけれども、ものすごくこう自分がアートに対してやってきてたことは、チャーハンでもできるんだっていうことが分かったみたいな。
[江良]
なるほどね。それはでもだいぶこう、大きな何か、大きな転換とかきっかけですね。だからこう、でもそうなって、月にじゃあ20万、そして豊嶋さんはまず10万はまず最低限稼いで、家計に入れるっていうふうになって、その引っ越しも重なって、そうしたらじゃあもう、働く時間が東京の時と比べると、何分の1みたいなことになったってことですか、まずは。
[豊嶋]
そうです。それでそのこっから、ちょっと時期がかぶってたんですけれども、登山が始まって。で、ある時、雪山っていうか、冬も山に来るのが好きだったんで、で、ある時、春の残雪の時期に、槍ヶ岳って北アルプスに行ったら、なんかスキー持った人がいて。
[江良]
槍ヶ岳で。
[豊嶋]
「え、こんなところでスキーするんですか」って、すごい思って、で、そのおじさんがね、その斜面をずっと見てるから、「え、ここをスキーで滑るんですか」って思わず聞いたら、「あ、テレマークなんだけどね、もうちょっと雪が柔らかくなるの待ってからかな」みたいな感じのことを言ってて。で、ちょっと意味がわからなかったんですけど、テレマーク??みたいなとか、雪が緩んだら行くってどういうことや、だったんですけど、お昼近くになって、そこ山小屋の前だったんで、僕もそこで休憩してたりしてたら、その人が、その斜面をテレマークスキーって言われる道具で、シャーってこう華麗に滑って降りてるのを見て、「うわ、すごーい!」って思って、テレマークスキーやってみたいな、あれは、とか思ったんですけど。それでもうそのまま帰りに、また中央線に乗って、東京まだ住んでたんですけど、帰る時に、もうそのまんま新宿とか行って、「すみません、テレマークスキーって何ですか?」みたいな、アウトドア、スキーショップに行って聞くみたいな。で、もうなんかやってみようみたいなもので、それがこう、引っ越しの時期とか、いろんなところと重なってたんですよね。
(photo : Kazushi Ojiri)
[江良]
ちなみに、テレマークスキーって、まあ、たぶん初めて聞く方も結構多いかもしれないんですけど。
[豊嶋]
テレマークスキーはね、今の現代スキーの、元になったスキーと言われてるんですけれども、テレマークって言葉自体は、ノルウェーのテレマーク地方っていう場所があって、テレマーク県になるのかな。そこで生まれたスキー、テレマークスキーって言われてて、なんかあの、クロスカントリースキーとかで、かかとがパカパカ上がってるような細い板のやつは、知ってる人多いと思うんですけど、まあ、あれと仕組みは同じなんですけど、かかとがロックされてなくって、かかとが上がりながら歩くように滑っていけるんですけれども。それが時代を経て、もっとアルペンスキーと同じようなぐらいにしっかりした板で、しっかりしたブーツで、でもかかとが上がるんですみたいな、独特の片膝を折ったような、スキーのジャンプの時に着地でテレマーク入りました!みたいなやつ。あのテレマークもそのテレマークで、足前後にずらした、ボクサーの前後の足みたいなとか、剣道をやる人の足みたいな、ああいうスタンスですね。
[江良]
それはあれですね、動きやすいっていうことなんですか?
[豊嶋]
かかとが上がるから歩きやすいんですよね、スキーでの移動がすごいしやすくて、バックカントリースキーって山に入っていくようなスキーする人にとっても、登っていくのも、そのスキーだとすごいやりやすくて。今となってはアルペンスキーでも同じようなことができるような機能が、できるようになってきたんですけれども、ちょっと前まではテレマークスキーじゃないと、そういう山に入っていくのが結構やりにくいみたいな感じだったんですけどね。歴史的にはテレマークスキーが先にあって、それがヨーロッパに伝わっていって、アルプスの方に伝わっていって、軍隊とかの冬の移動手段で使われるようになった時に、アルプスの山なんてすごい急峻の山が多いから、それをこんなに足ぐらぐらするやつでは無理だってなって、ロックしたアルプスのスキーでアルペンスキーっていうのが生まれたんです。
[江良]
なるほどね。
[豊嶋]
テレマークスキーは今でもあるんですけど、やってる人もめちゃくちゃ少なくて、テレマーカーがインスタグラムとかで写真を上げてるハッシュタグで「#かかと上がる人大体友達」っていうハッシュタグがあるくらい、それくらい狭い世界で。
[江良]
狭く濃いコミュニティになっているんですね。本当に、豊嶋さんのご自宅にもテレマークスキーが今ここ話している場所から。写真をちょっと後でウェブサイトの方で見ていただければと思いますけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。
[豊嶋]
あれはこっちでニセコをベースに活動されている高梨さんという方、テレマークのレジェンドなんですけど、その方がニセコの工場に制作を依頼して、自分のデザインしたスキーブランドを作ったんですけど、それのウェブサイトの制作の方で手伝いとかしてたりして、で僕もあれを何本か持ってるんですけど。
[江良]
でも、本当にそれで、15年前?
[豊嶋]
ぐらい、ビッグバンがね。
[江良]
ビッグバンがあって、同時期ぐらいに槍ヶ岳というビッグバンもあって。2019年に石巻のリボーンアートでご一緒させてもらった時も、豊嶋さんはほとんど山にいるよーって言って、特に冬はもう北海道で、バックカントリーで山登って行って、1本滑ってきてみたいな。それはでも、福岡移られて自分の仕事の、これぐらいお金が必要で、そのためにこれぐらい働けばいいから、このぐらいの時間が自分で好きなことというか、仕事以外のことに使えるようになるということが分かって、その中で自分の興味がある山登りとか、スキーとか、そういうところに迷いなく、突き進んで行かれてったみたいな。
[豊嶋]
そうですよね。普通だと、そんだけスキーしかしてない期間が、毎年4か月も5か月もあったら不安になると思うんですけど。
[江良]
みんな、豊嶋さんって自由だね、みたいな、なんでそんなことできるんだろうっていうようなニュアンスも含めて、みんなで話してたりしたんですけども、そういうような、カラクリというか、そういうようなロジックがあって、生き方を組み立てていかれたということなんですよね。
今、これ真狩も、本当に目の前に羊蹄山が、すごい綺麗に目の前に見える場所なんですけども、これもだから、スキーでここに来てたから、ここを選ばれてるということですよね。
(ニセコ連峰)
[豊嶋]
そうですね。これはもう自分の生活の方法論みたいになってますけど、あんまり自分で選んでないんですよ。そもそも真狩村に来ることになったのも、graf時代の友達とかと、スキーに行くよ、北海道のスキーに行くよっていうお誘いがあったんで、俺も行きたいってなって、来たのが15年前です。それが真狩村だったんですよ、たまたま。
僕は北海道ろくに来たこともなかったし、北海道でスキーするのも初めてだったんで、まだ全然始めたてで下手くそで、そんな時だったんで、どこでもよかったんですけど、それを一緒に来た、真狩村に来た時に、grafの友達っていうのも真狩村に住んでる友達を訪ねていく形でここを選んで、ここに来たので、友達とかにこっちにも一緒に滑るようになったんですけど、真狩村に在住の友達っていうのもテレマークをする人で、そういう繋がりもあって、「僕はテレマーク全然うまくならないわって練習もっとしないと」みたいなこと言ってたら、その友達が「うち一部屋余ってるから、もうそこでいていいですよっていうか、合宿したらいいじゃないですか」って言ってくれて、「それ本当に行っていいの?」って言うと全然OKですよって感じだったんで、じゃあ、みたいな感じで、その年は何回か往復しながら来ただけだったんですけど、その翌年ぐらいから、「じゃあ本当にいいっすか?」みたいな、「全然いいっすよ」って、「そのかわりに俺、ご飯を毎日作るっていう仕事を担当するから」って言って、そこは夫婦だったんですけど、二人とも働いてたから忙しいから、晩ご飯作ってくれる人がいるっていうのは結構重宝がられて、それで「掃除とかも別にするんで、掃除とか食事のことをします」みたいな感じで言っていたら、帰る時に「次はいつ来てくれるの?」みたいな話になって、来年はもうちょっとって2ヶ月になり、3ヶ月になりみたいな感じで増えてったんですけど。でもそのうちに彼らが転勤で札幌に行っちゃうことになったので、もうそこには住めないってなったタイミングで、その真狩村でカフェをやっている、また違う友達がいるんですけど、そのカフェを作る時にちょっとデザイン手伝ってみたいな感じのこともあったカフェなんですけど、「行くとこないならうちのカフェのロフトスペースでよかったらどうぞ」って言ってくれたんで、そこは8年くらいあそこから、僕は除雪をやりますということで、そこにいさせてもらってたんですけど。だからこのニセコエリアっていうのは他にもいろいろな場所があるんですけど、真狩村っていうのは僕がもう選んだというよりかは、そういうところでいて、で、そこがたまたま羊蹄山の僕たちがいつも滑ってる斜面にアクセスが一番いいのが真狩村だったりとか、なんかそういうのもあったので、この場所にずっといるみたいなのが始まったんですよね
(羊蹄山から見下ろす真狩村)
[江良]
どういうきっかけでこのお家を持つこと、しかも自分たちでお仲間と一緒に自分で作るということに、どういう経緯でなっていたんですか?
[豊嶋]
それはね、あの僕出身が大阪で、両親が大阪にいたんですけれども、だからいつか介護とかがたぶん始まるなと思ってて、なので福岡に住みつつも大阪に戻っては、実家の2階とかを一角を一部屋を片付けたり自分でして、介護生活が始まったら、ここを自分の部屋にして、仕事もここでできるように、Wi-Fiとかも勝手に設置したりとか、いろいろして、来るべき日の準備みたいな感じでやってたら、ある夏に、4年前かな、4年前の夏に父が急に亡くなり、その半年後の冬に母親も亡くなりみたいなことになって、介護とかがなくなるとともに、介護で大阪に帰らなければならないという事自体がなくなったので、弟はまだ大阪にいるので、お墓どうする、みたいな話もやってきて、母の葬儀だ何だみたいなのが冬だったので、北海道から駆けつけたんですけど、帰りの飛行機の中で、もしかしたら大阪に行くこともほとんどないかもって思って、飛行機が向かっている北海道には、もしかしたら北海道にもう、住んでしまってもいいのかもとか。
[江良]
まあでもね、結構長い時間をここで過ごされてますもんね、それも。
[豊嶋]
というふうな、こう、ふとしたなんかそういうこともあり得るのかっていうふうなことを思って、それで、北海道に帰ってきて。でね、あの知り合いのね、そっからほんとすぐその春だったんで、2ヶ月後くらいに同じテレマークをやる仲間と、あるガソリンスタンドでたまたま会って「最近どうしてる?」みたいな話になって、「いや両親が亡くなって大阪に行くことなくなるので、北海道に住んでもいいかなとか思ったりしてる」って言ったら「真狩だといいよね。てか、おじさんいるからちょっと聞いてみるわ」って。「え?」って言ってたら、次の日に電話がかかってきて、「なんかあるみたいだよ、と。ちょっと見に行こうよ」って言って、一緒に来てくれて、見に来たのがここだった。その親戚のおじさんが「ここに住めばいいわ」とか言ってくれて、住むことに、もう「わかりました」みたいな。っていうのがここだった。だから何も他のいろいろ探したわけじゃなくて、
[江良]
巡り合って
[豊嶋]
巡り合って、ここにじゃあ、ってなったんですけど、なんで自分たちで建てることになったかっていうのは、そんなに潤沢に予算があるわけじゃない、もう全然仕事してないような、稼ぎを極力減らしてる生活してたから、ないんですけど、親が少し残ってた、自分たちの介護用に置いてたお金が使わずにあったから、それ相続して、弟と半々だったりとか、そんなんをちょっと使わせてもらいながら、同じテレマークの先輩の大工さんに、「こんなこんなで、ここに何か建てたいんですけど、こんな予算で何かできますかね?」って言ったら、「その予算でできることはできるから、まあやろうよ」みたいなことを言ってくれて、それでできるサイズがこのサイズだったりとか、その代わりに僕も一緒になって、その分、安くつくわけだから、他の職人を入れるよりかはってことで、3人全員テレマーカーで。
(家を建てる前 / 間取りに沿って並べられた角材)
[江良]
やっぱり濃いですね、テレマーカーの絆が。
[豊嶋]
テレマークのコミュニティは結構あって、それで一夏かけて3年前の夏にここを作った。でも中とかは自分でやっていかなければいけなかったんで、冬の間中、ごそごそ、工事現場に住んでるみたいなのから始まって、やっていってる途中。
[江良]
ある意味、プロパンガスは契約はされてるけれども、プロパンガスって何か管が繋がってるわけじゃないから、完全、インフラも含めて、オフグリッドの空間ですよね。
[豊嶋]
今もオフグリッドも、オフグリッド生活をしてみようと思ったわけじゃなくて、それもここに住めばいいっておじさんが言ってくれた時に、こんな普通の道から離れてるところに150メートルくらいに入ったところにあるから、除雪も大変だし、電気とか水道とかも無理じゃないですかって言ったら、水道も電気も引けるし、土木工事はこっちでもユンボあるから、やってあげるし、除雪もなんなら俺が、朝夕入ってあげるから大丈夫だよって言ってたんですけど、いざ、蓋を開けてみると、家を建てるってなった時に調査してもらったら、ここは村の給水地域に入ってないから、ルール的にここに水道引けませんよって話があったりとか、電気も埋設するのの引き込みが、発電と送電が分離化してからは、北海道(管理)の道までは、北電がやってくれるけど、そこからの引き込みは自己負担ですよって言われて。それを見積もらったら、それだけで500万円かかるとか、それはもう無いですってなって。だからもう電気も、水も近くの沸き水汲みに行くかとか。電気もソーラーパネルでやっていくかみたいなのを想像して、その当時ずっと北海道から九州帰る時とか、サーフィン行く時とかも、ジムニーをね、ちょっと中で寝れるように改造してたんですけど、それで年間ジムニー泊、何日ぐらいかなって思ったら、結構60日以上はジムニーで暮らしてたっていうのがあったんです。結構やってて。帰りも北海道から九州帰るのにわざわざ1ヶ月くらいかけて、あちこちの山を滑りながら帰るんですけど。なのでジムニーに比べたら、これ余裕でしょっていう。変な自信が湧いてきて、水も汲みに行けばあるし、ソーラーパネルでもある程度行けるでしょみたいなのがあって、ガスだけはプロパン屋さんが、別に全然運んであげるよって言ってくれたんで、ガスは契約してるんですけど。だから、いけるのかなとか思ったけど、そういうことでオフグリッドって呼ばれるような、ライフスタイルになり。
(湧き水を汲むところ)
[江良]
結果として。
[豊嶋]
そう、結果として。でやってみたら、それに関しては意外と全然大丈夫っていうのも分かって。ソーラーパネルも、そういうことやってる人に、少しだけ話聞いたりとかもしたんですけど、結局、300ワット発電するパネルを4枚。だから理論値的には1200ワットを、南向きの壁面につけてるんですよね。こっち雪降るから、屋根の上につけると、東京とかみたいに屋根の上につけてても、雪で埋まって全然発電しなくなるので、南側の壁面につけるっていうのは、結構事例があるよって教えてもらって。雪国は、垂直に設置するから壁面に、雪つかないから、いいっていうのと、あと雪の反射した光をパネルが拾うんで、上から普通にまっすぐくる太陽光と、雪面を反射した太陽光も両方くるから、結構いけるっていう風に聞いて、やってみたら本当にすごいいける感じだったんですけど、その時も、さっきのULハイキングのギアリストとか、幸せの見積書と同じで、一体自分が何ワット1日使うんだっていうのを、また緻密にパソコン、MacBook Air、何ワット、充電するのに何ワットとか、冷蔵庫はこれかなみたいなとか、とにかく電化製品っていうか電気必要な製品を、電球1個から全部ワット数とか、それの想定される使用時間とかでかけていって、1日の総電力みたいなのを自分なりに出してみたら、こういう常に絶対に使うっていうのは、600ワットぐらいだったんですよ、常に。あとオプションで、例えばさっき言った、パソコンとかは晴れてる日に充電して、結構天気悪い時はその充電で乗り切るみたいな、こともできるものも、充電式のものを増やしたっていうのが1個のやり方で。でも一番電気食うのが、例えば冷蔵庫みたいな、24時間ついてるって、というようなものが累積していくと、すごいワット数になるみたいなのが多くて、だから、そんなのでも、何ワットだったらこうなるっていうのが分かったので、じゃあ、蓄電池は3000ワットのやつにしたんですけど、そうすると600ワット、多く見ても800ワットぐらいで、4日ぐらいはいけるかも、みたいな、3000ワットあればね。だから、発電0でも3、4日はいける。発電0が3、4日続くってことはあまりないんで、いけるんじゃないかと。あと一応バックアップで発電機をつないでて、本当に無くなったら発電機で発電すればいいという状態にして、やってたんですね。そこもまたリスト化して。
[江良]
ちゃんと見て。
[豊嶋]
じゃないと何枚パネル入れるかとかも分かんないですよね。じゃあ計算しようって考えでスパッと行き着いたのは、ULハイキングのメソッド。
[江良]
ULハイキングのメソッドが体に染みついて、そういうアート的な、アート的な。
[豊嶋]
そういう方法が。そうすると、無駄にパネルいっぱいつけるとか、結局パネルいっぱいつけるということは、いっぱいお金使うってことだし、蓄電池もやたらデカいものの方が安心だって言っても、そんなの半分も使わないでしょぐらいのやつ持ってても仕方ないわけで。
[江良]
でもそういうULハイキングからメソッド的にやってきて、ここでも生きていける、活かしてやっていくっていうのと、同時にこういう場所を作られて、カフェのロフトからこっち移ってきて、新しく得られたものというか、気づいたこととか、そういうことってあります?
[豊嶋]
それはね、さっきのまたアートの話って今度は再接続されていくんですけど、日々DIYをめちゃくちゃするんですよ。2年目の夏には、除雪機とか、いろんなものものが、家自体は狭いので、あちこちに置いてたんですけど、やっぱり納屋がいるってことで、今度は先輩大工さんにもう一人でできるよとか言われて、えーとか言いながら、次の夏に一人で作ってみたり、だからめっちゃ大変だったんですけど、
(セルフビルドした納屋)
[江良]
大変ですよね。
[豊嶋]
大変だけど、ひとつひとつの作業は大したことないんですよ。量って、木を量って切る、そしてビスで留めるみたいな作業のひたすら繰り返しがあるんで、だから間違えたりもするんで、しょっちゅう。で、あー違う違うって一人で言いながら、また間違えたーって言いながら。だけど、ひとつひとつの作業は大したことないので、それをひとつひとつやっていくみたいなのの、果てにできたみたいな感じだったんです。ギリギリ雪降る前にできてよかったみたいな感じで、今年は家の中とかでまだできてない、ここに棚がほんと欲しいとか、ここはまだ放置されてるとか、そこにこんなにこれをハンガーをかけるなんかをつけようとか、あとなんか家の周りにデッキがあったらいいなとかっていうのも、どうせやったら家のちっちゃいから、デッキは広くしようみたいな。今それ真っ最中なんですけど。だからなんかその、さっき言ったように、仕事の分量を減らせて、あとじゃあ遊んでるかーって言われると、まああの、忙しくはしてるんですよ。朝起きて、結構8時からこのDIYの仕事が始まって、5時まで。10時に休憩して、12時にご飯食べて、3時に休憩して、夕方5時に終わりみたいな。で、またそこから温泉に風呂入りに行って、それからご飯作って、9時とか10時に寝ちゃうみたいな。また次の日5時に起きてとか。結構、いわゆる仕事はしてないんだけど、忙しくはしてて。だけど、やってることが、お金を稼ぐためのいわゆる仕事ではなくて、DIYでなんか作るって、自分の生活そのものを作ってるという作業と言ってもいいと思っていて、なので、ここに例えばデッキを作ったら、自分の生活が結構ガラっと、ここ外に出て開放的、気持ちいい、ここでビール飲んだら、ってなれるっていうのは、生活様式がガクって変わると思うんですよ。そこに納屋ができたから、ごちゃごちゃあったものが全部そこにすっきり収納されて、あー快適とか。だから、その作業は、お金を貰うような仕事をして、銀行にお金が振り込まれるっていう、報酬じゃなくて、生活そのものが変わるっていう報酬が受けられるっていう、そういうことだなって風に思って、農家さんが、地主さんとかも、今もジャガイモがボコンっとケースごと、はい食べて!って持ってきてくれたりとか、それを一生懸命料理するとか、っていうのは、フライドポテトを昨日の夜も作ったけど、
(納屋の制作ノート)
[江良]
無茶苦茶美味しかったですね。
[豊嶋]
あれを買ってくるんじゃなくて、いただいたジャガイモを、ちゃんと美味しいフライドポテト作れるように、やり方を調べたり、友達に聞いたりして、料理することができれば、それは生活で、自分の生活にダイレクトに帰ってくるじゃないですか。だから、やっぱ、一回お金を稼ぐために仕事をして、それによって得たお金で自分の生活を変えていくっていうのは、結構遠回りだなっていうふうに思うようになって、この家を建てた経験から。この家もちっちゃいけど、住宅メーカーとかに頼んで建ててもらったら、到底払える金額じゃないものが必要で、そのためにいっぱい仕事しないといけなかったと思うんですけど、自分たちで建てたり、自分で建てたり、自分で作ったりしていったら、意外とお金がかからずできる。だから、仕事以外の時間に、もうやってる作業は大して変わらないかもしれない。人のためにやったらお金もらえるけど、自分のためにやったらもらえないっていうだけで、やってるのは木を計って切って、ビスで止めてるっていう作業かもしれないけど、自分のことをやるっていうのは、報酬がダイレクトに自分に返ってくるっていうのは、ロスがなくて、めちゃくちゃ上手い方法だなって思ったんですよ。幸いここちょっと村外れみたいなところでもあるから、外で作業してても気持ちいいし、作業自体も自分のやつなんで、いつまでにっていうのは、自然に合わせて、雪降るまでには終わらしたいとか、自分都合の締め切りはあるかもしれないですけど、いついつまでに納品しないとダメだとか、そういうことも別にないので、ある程度自分で調節しながらやったらいいだけのことだし、だからそれは、家事全般に言えるねっていうの。掃除も自分ですれば、ルンバとかを買って、ルンバに掃除させるよりかは、ホウキを新しく買ったんですけど、そのホウキ結構いいホウキで、それで掃き掃除を毎朝するんですけど、そしたら、自分でやって自分で気持ちのいい空間、その瞬間手に入るっていうのは、そんなに高いルンバとか買わなくていいみたいな。なんかそういう、何て言うんでしたっけ、主婦の人の労働が、家事に対する労働の金額が、全然低くしか見積もられてないっていう社会的な問題にもちょっとなってますけど、それと同じなんですよ。本当はだから、家事なんて月100万とか200万とかぐらいの仕事だと思うんですけど、それ自分でやったら、その分、稼いでこなくていいんですよね。それもまた同じループの仕組みがあるなと思ってて。
[江良]
やっぱりそういうの、都市だとお金をどういう形かで稼いで、何にするにしてもお金と何かモノなりサービスを、インフラも含めて交換していかなきゃいけないから、お金の方がすごい価値があって、家事みたいな自分の生活を作っていくようなものは、あんまり高く見積もられないみたいなところがあるかもしれないですね。
[豊嶋]
そうですよね。
[江良]
こういうところに来て、自分で生活を作ったり、自分の手でやれることの中で組み立てていくと、逆に全然そこが転換して見えてこられたのかもしれないですね。
[豊嶋]
だから、この村、村内にそんなにいっぱい食べに行くところがあるわけじゃないんで、基本的に3度の食事は自分で作るっていうことになるんですけど、もともと料理はする方でしたけど、ここにいるようになって、絶対するっていう感じになってきたから、料理の腕は上がりますよね。
[江良]
だし、どれくらいの広さですか?
[豊嶋]
ちっちゃい畑があって
[江良]
ちっちゃい畑があって、そこでトマトとか、むちゃくちゃ美味しい。
[豊嶋]
うちのトマトを江良さん一人で多分30個くらい食べてたんだよね。笑
[江良]
昨日、フライドポテトを作っていただいて、あと、ラタトゥイユを作っていただいて、もう、もぎたてトマトをボウルに出していただいて、あとね、美味しいパンがあって、十分満足というか、栄養的にも。
[豊嶋]
そうですね。ほぼタダみたいな。笑
原材料ほぼタダみたいな世界なんですけど、やっぱりそうやって自分の生活技術を上げていったら、いわゆるQOLにダイレクトに帰ってきますよね。
[江良]
そうですね。
[豊嶋]
だからDIYできるようになったら、どんどん自分の住空間を快適にしていけるし、料理を上手になったら、毎日美味しいご飯を安くで食べられるようになるし。でもそれに必要なのはやっぱり時間なんですよね。お金じゃなくて。時間を作れないと、それはやっぱりできなくて、時間さえ上手く調節して手に入れれば、逆にお金がそんなにかかる生活じゃなくても、たぶん幸せにやっていけて、そのためには、一体いくらだっていう計算が根拠がやっぱりないと、単に仕事ちょっと減らしたりとか、パートタイムに変えましたとか、やってしまったら、全然足りない、やばいとか、これなんか、老後の貯金まで全部使っちゃってるとかさ、それはまた違う不安に今度、苛まれることになると思うんで、やっぱりいろいろ荷物の重さを測るという作業は、すごい生活の中においても、めちゃくちゃ有効だなっていうふうに。で、あと、自信が持てますよね。こんだけ稼いでけば一応大丈夫なんだって思ってたら、何にも稼いでない時期があったとしても、不安にならないっていうか。もう稼いであるから大丈夫っていうかさ、こんだけね。だから、それはすごく使えるテクニックだなっていうふうに思うから。キャリアはね、すごい転職して、キャリアアップして、さらにいい給料とか条件いいところに、っていうふうなことが、結構ね、やる人多くなってきてると思うけど、なんでその給料をもっといるのか、一体いくら上げれば自分が満足で幸せなのかっていうのが、見えてない中で漠然とさらにいい給料とか、さらに所得をもっと上げていこうっていうのは、時間も無駄だし、そこでの楽しい仕事だったらいいですけど。
(タイルを張る作業中)
[江良]
お金のためにっていう事が先に来ちゃうと、楽しくないこととかもいっぱい我慢していかなきゃいけないし。
[豊嶋]
それは、効率が悪いなっていうふうに思えるように。思ってたけど、さらに思うように、こっちの暮らしをしてたらね。結構、本当に田舎で暮らしてると、東京もたまに仕事で行きますけど、なんかすごい遠くからそういう世界を見てるような感覚にもなることが多くて。で、たまに東京行ったら自分が東京行ったら時代のことも思い出しますけど。なんか、あの時間はあの時間で自分にとっては必要な時間だったと思うんですけど、あのまま行ってたらどうなってたのかな、みたいなことは、たまにね、帰って小田急とか乗った時に思うんですよね。で、自分でそんなに選んだわけじゃないけど、流れでこういうことになってて、自分はすごく、どっちが良かったとか、パラレルワールドのことは分からないにしても、今に満足できてるから、それは幸せなことだなっていうふうに思ってますね。
[江良]
なんかでも逆にこっちに来て、困ることっていうのはあるんですか?
[豊嶋]
困ることはあるんですけど、細かいことはね。でもなんか解決されていくんですよね。そういう、なんか、「除雪機が壊れた!やばい!」とかも、なんか、そういうのって、その時はわーどうしよう、とか思うんですけど、大体のことはなんとかなるぐらいに、ちょっとこう、図太くなっていくっていうか、特にこういう豪雪地帯とかね、いたりしたら、なんか。
[江良]
都会の方が良かったとか、そういうようなこととかはもうあんまないですかね。
[豊嶋]
住むのは、もう結局6年ぐらいいたんで、東京。東京、神奈川で6年ぐらいいたんで、首都に住むみたいなのはもう自分としては満足してて、ただやっぱここにいると、カルチャーロスみたいな。映画が観たいとか、展覧会見に行きたいとか、なんかこの芝居が見たいとかさ。なんかそういうのが、だから東京に行く用事に引っ掛けて、めちゃめちゃどこどこ美術館にいま何やってるのとか、めっちゃ調べたり、その展覧会に合わせて仕事の調整したりとかして、東京行ったら、本当にもう、あれ行ってこれって、あれ行って、みたいな。観光客と本当に同じ動きをしてます。
[江良]
でも、それはそれで楽しそうですね。選ぶし、まあでも行けばいいというかね、
[豊嶋]
そうですね。
[江良]
仕事作る、まあ豊嶋さんだと仕事作ればいいとか。
[豊嶋]
まあその日でいいですか?って聞いて、いいですよって言ってくれたら、それで合わせて行って、1日多めに滞在して、その日はそれで見に行くとか、まあ結構逆に楽しみになってます、東京行くとかね。都会やー、みたいな。笑
[江良]
すごい、ロンドンとか東京とかの都会を一線でやってた人が。
[豊嶋]
まあそうですね。あと、これは真狩村に住むようになってじゃないんですけど、さっきの仕事の話とかに絡むことで、仕事をしないで遊んでばっかりだねみたいなことを、いいね、みたいに言われるんですけど、じゃあ仕事って何ですか?っていうのが、やっぱり自分の中に大きな問いとしてずっとあって。僕の中では仕事って普通、なんかこうお金を稼ぐことを仕事っていうふうに定義して、それ以外の例えば趣味的なものを遊びみたいに、言うと思うんですけど、スキーとかね。プロスキーヤーじゃない限りスキーを遊びだと思うんですけど。だけどそういうくくりじゃなくて、自分のやることっていう、to doに対して、お金が得れるものと、得れないものと、むしろ払うものがあるっていうか、1日の中の。1日の中のto doリストをばーって作ったら、例えば朝起きて歯磨きとか、あれは何ですかって言ったら、遊びですかって言われたら、いや、遊びでもないし、仕事でもないなって。まあなんかお金は別にもらえないけれども、遊びでもない、生きるみたいな、直接のことだと思うんですけど、その3つで区別していったら、僕の場合スキーは、むしろ払うことになるんですよね。なんか道具買ったり、スキー場にも行くんでリフト券買ったりして、やることの中の払うものっていうくくりに入ってて、例えばハッピーハイカーズっていう活動を、仲間と一緒に九州でやってるんですけど、そういうコミュニティの運営って、やってる中身は、本当にこれは、他のお金もらっている仕事と、まったく同じような作業をしてるけど、みんなボランティアで集まって、勝手に融資でやってるだけなので、一銭ももらえないんですけど、でもやってる作業は完全にお金もらえるような作業を、だけどもらってない、払うこともないんですけど、お金はもらえないようなやることを、日々やっててとか、いろんなことやって、一日、いろいろなto doをこなすじゃないですか、その中にお金がもらえるもの、もらえないもの、むしろ払うものっていうのを、3つの分類で考えたら、結構すっきりしますね。これ、例えば僕はDIYで、今デッキ作ってるのは、やってる作業としてはバリバリ仕事っぽいけど、これも材料を買ってるから、むしろ払うものとしてやってるとかね。to doリストをちゃんと、お金をもらうもの、もらえないもの、払うものっていうバランスを、to doリスト内でしっかり持ててたら、破綻しないんじゃないかなと思って。
(自宅の窓からの景色:秋)
[江良]
でも本当に今日は、いつも最後の方に、都市生活者がどうやって、自分の暮らしをアップデートできるかというか、そういうヒントみたいなものを、ゲストの方にお伺いするんですけども、今日はもう全編、いろんなヒントだったり、自分が自由になっていく、時間を作っていく、仕事をどう捉えていく、ちゃんと幸せも含めた、自分の生活コストも含めて、ちゃんと家計簿を作っていくとか、全編、そういうヒントが満載でしたね。
[豊嶋]
そうですかね。でも、キチキチキチキチやってるわけじゃないんで、それ自体も、リスト作る作業も、意外と楽しかったりするし、へぇーって思うのも、そうかーっていう感じもあるから。
[江良]
そうやって自分の足元というか、どこに生きてて、何働いててみたいなものを、特に都会で組織とかに属して働いたりすると、その組織の流れとかの中に巻き込まれて、よく分からなくなってくるというか、自分自身で何を選んでるのか、分からなくなるようなことって、結構起こる人は起きると思うんですよね。だから、今、豊嶋さんおっしゃっていただいたように、いろんなものをちゃんと見つめ直していくというか、その中で自分の大切なプライオリティをつけて、選んでいくということが、でもまあ、都会だとね、やりにくいことあるけど、取り入れられることはありそうですよね。
(自宅の窓からの景色:冬)
[豊嶋]
うん、まあその自分の人生の必要な金額っていうのは、結構いいと思いますよ。使えるっていうか、はっきりクリアになってくると思いますね。なんかね、あの神奈川にいた時、これは載せない方がいい話なんかもしれないけど、分からないけど、まあいいか。ちょっと大きい仕事場が必要だった時期があって、制作物がでかくて。東京都内では、そういう大きな作業スペースというのを確保するのに、あまりにも高くなりすぎるからって、いろいろ探したら、神奈川の綾瀬市っていうところに、厚木の方なんですけど、そこで物件があって、そこで制作することにしたんですけど、当時、中野に住んでたんで、ちょっと通うのが遠すぎるっていうので、神奈川に引っ越すことになったんですけど、座間市っていうところに行ったんですけど、だから小田急線に乗って新宿へ行ったりすることが多くなったんですけど、ある日、小田急に乗ってたら、帰りに小田急の駅ってOdakyu OXってスーパーが大体あるんですけど、そこで買い物してる人いっぱいいるし、小田急降りてね。で、もしかしたら、その小田急に乗って、小田急のデパートとかで働いてる人とか、いるやろうなと思ったり、小田急不動産で家買ってる人もいるなと思ったら、小田急で働いて、得たお金を全部小田急に返してるみたいな、そういう図式があって。これはもう電鉄会社とか、多分、そんな仕組みだと思うね、
[江良]
どの私鉄でも、やってらっしゃるやってるじゃないですか。
[豊嶋]
それ多分分かりやすいパターンなんだけど、もうちょっと広範囲で社会で見たら都市生活って多かれ少なかれそうなってるなと思うんで。だから稼いだお金を全部東京で稼いだお金を全部東京に返してるみたいな感じになるから、意外と自分のために残らないっていうかね。なんかそれも結構気づいた時にゾクッとしたね、それは。
[江良]
そこからどうアウト、外に出れるのかっていうのは、都市の中にいる限界みたいなものが、確実にやっぱりありますよね。自分の手でトマト作れる、小屋も仲間と作れる、生活も作れるっていう、水は汲んでこれる。そういうことから、何かね、そういうところから出れる、具体的な手段みたいなものはありますもんね。
[豊嶋]
まあでも、ぶっちゃけで言うと僕はもう何でもいいんですよ、多分。笑
[江良]
一周回ってきて。笑
[豊嶋]
そうそう。もうなんか、何でもいいから、出来ちゃったみたいな。家もこういうデザインがいいとか、こういう木を使いたいとか、こういう広さがいいとか、あれば、多分、建ってないと思うんですよね。やっぱり予算的に無理とかさ、もっとこうしたかったけど、それだったら予算が、もっとコストがかかるからどうなのとか、色々あるけど。その大工の先輩にあって、この金額で出来るのは何ですかみたいな。じゃあもうやってみようかみたいになったので、そのデザイン的な設計作業って、やらずにスタートしたんですよ。この辺にキッチンで、ここにトイレだねとか、ここに階段だね、ぐらいなんで。窓の位置は決めてくれていいよ、みたいな。そんだけで出来たみたいな感じなんですけど、だけど自分はそれでも全然満足できてて、なんで満足できるのかって何でもいいからだと思うんですよ。
(フィンランドにて)
(写真: 鐵艸 将啓)
[江良]
こだわってる部分が、軸にはあるけれども、そういう柔軟さというか。
[豊嶋]
方法にはこだわっているところがありますね。リストを作るとか、あと何でもいい式みたいな。方法は多分自分なりに、だいぶ板についてきた方法にはこだわるというか、それを使っていると思うんですけど、出た答えに関しては、全然、逆にあまり興味がないと言ったら変ですけど、なんでもいいわみたいな。
[江良]
でも結果的に満足できてるから、多分そのやり方でやっていければ満足できるっていう、何か自信というか確立というか、豊嶋さんの中で確立していらっしゃるんでしょうね。
[豊嶋]
それをもうちょっと話していいですか?
[江良]
どうぞ。
[豊嶋]
それはね、人から教えてもらったんですけど、直感的にそういうことばかりしていった時に、graf時代の話ですけど、家具とかインテリアとか建築って、やっぱりデザイン、設計という作業は大事じゃないですか。設計してそれでコスト出してで見積もり作って施工していくっていうやり方なんですけど、自分がやってたアートみたいなものって、別に設計図なくても、例えば絵を描くために、下絵とか、修作作る人もいるけど、そのままベーってやる人もいっぱいいたりとかして、だから設計図に基づいて作っていくっていうよりかは、これ何かに使えそうとか、これいいよねみたいな感じで、それをこう、たまたまそこにあったものを、寄せ集めて、これちょうどいいやみたいな、これでいいわっていうやり方っていうのをやってた時に、国立民族学科部物館のある研究者の先生が「今度ブリコラージュっていうのをテーマにした展覧会やるから、そこで空間担当しくれない?」って言ってきて、「なんで、僕に頼むんですか?」って言ったら、「豊嶋さんっていろんなこと、かなりブリコラージュ的にやってるなと思って」って言われて、「ブリコラージュなんですか」みたいな話をやって、その時に、これよくいろんなところで僕が話すことなんですけど、だから、主婦のカレーとシェフのカレーの違いって言われて、それ意味分かりませんって言ってたら、まずシェフのカレーっていうのは、決まった材料で、決まったレシピで、決まった味、決まった料理して、決まった値段で提供して、美味しいって思ってもらえるのが、シェフのカレーなんだけど、主婦のカレーっていうのは、ジャガイモいっぱいもらったから、ジャガイモいっぱいのカレーにしようかなとか、肉があると思ったけど、ないから、ソーセージとか入れてみようとかそんな感じで作ってて、最終的に、あれ、ここにカレーのルーがあると思ったけど、シチューのルーだったんだって、カレーでさえなくなってシチューになっちゃったとしても、家族が美味しいなって言って、お腹いっぱい食べれて、栄養もついてっていうもんであれば、別にカレーじゃなくてもいいやぐらいな、着地点でもOKになれるっていう話をしてくれて。で、なるほど!ってその時、本当にもうそれはなるほどと思って、今まで自分なりの直感でやってたことに、それでいいんだっていうことで、○印ー!みたいな、もらえた、みたいな感じになったから、それ以降は単なる直感っていうよりかは、自分はこういう手法を手に入れてたんだっていうのを、ちゃんと自分で認識できるようになったから、他の人には、そういう謎なやり方してるって思われるかもしれないけど、これはもうブリコラージュでいきますっていうような。人生自体を、ブリコラージュの反対語が、対象的なことはエンジニアリングっていうね、設計していくみたいな。だから、こういう人生設計をもとに、こういう風にいくんだっていう風に考えてないタイプですね、僕は。
[江良]
でも結果として、いろんな巡り合いが、やっぱりそこに満足して、ここの場所と出会い、小屋を建てるっていう。そこが、そのいい出会い、巡り合いを、引き込んでいくような。
[豊嶋]
引き込むというよりかはね、エンジニアリング式だとね、例えば真狩じゃないんだよね、僕は海のそばの湘南に住もうと思ってるから、真狩の話があっても、お断りするみたいになっちゃうと思うんですよ。だけど、別にどっかで住めたらいいなって、ちょっと思ったくらいの。だからOK範囲がむちゃくちゃ広い状態なんで。
[江良]
ある程度、家計図で幸せだとか、こういうものがあって、これがこうだって、やっぱり整理だったり、そこができてるから、だから、巡り合った時の、この良い悪いとか、そういうところに巡り合っていくみたいなところは、その手法があって、結果として。
[豊嶋]
そうですね、巡り合いに乗ることができますね。
[江良]
乗ることができる、出会っていくことができるというか。今日はお話聞いててすごい思いました。
[豊嶋]
それはね、最近サーフィンもやるんですけど、サーフィンやってなかったら、ここの条件の、この土地受け入れられなかったかも、というぐらいのものがあって。
[江良]
波の一期一会みたいな世界があるんですね。
[豊嶋]
波乗りって、どんなにプロサーファーでも、来た波に合わせて乗るっていうことしかできないじゃないですか。波自体を自分で、もっと倍の大きさにするとかできないじゃないですか。だから、来た波に自分を合わせて、そこ波を滑っていくっていうことっていうのが、やっぱ、あるなと思って。だから、自分でその状況自体をクリエイトすることはできなくても、そこに出会った状況に自分が合わせていくみたいな。そういうのも、自分の一つの方法として、サーフィンから学んだことで。
[江良]
でも、その方が面白いっていうのはありますよね。面白いっていうのかな。自分の予測しないものに出会えた時に、反応できるっていうのは、クリエイションっていう意味では、何か新しいものだったり、思いがけないものが生まれる可能性を秘めているような気がします。
[豊嶋]
それを楽しむ方法を自分が持っていれば、一つの自信になっているので、そういう、ええ!っていうような、ここ水も電気もないの!って言われても、なんとかなるかもって思えるっていうか、そういうことにはなると思いますね。
[江良]
ありがとうございます。じゃあ、ちょっとTシャツの話してもいいですか?
僕がやっているインドのコットン農家の顔が見えて、そのTシャツも生産者と一緒に作って、オーガニックに転換していく、Grow Organicってプロジェクトなんですけど、今回はHAPPY HIKERSのイベントのチャリティTシャツを作ったらいいんじゃないかっていう話をさっきさせてもらったんですけど、もう一回、ハッピーハイカーズと、どういうイベントでっていうところとかからちょっと教えてもらってもいいですか?
[豊嶋]
HAPPY HIKERSっていうのは、僕が福岡に引っ越した時に、誰も友達いない中で、妻が住みたいって言ったから、そこに行くことにしたんですけど、山登り、友達もいないし、山登り行く仲間もいないわと思って、でも行ってみたら結構いい山いっぱいあるし、ハイキングしてる人たちもすごいいっぱいいるなと思ったので、そういう人たちが繋がっていけるような、ある種のコミュニティみたいなものをやっていくのは、自分の友達作りにおいてもいいんじゃないかと思って、やってみたのが始まりで、もうでも10年くらいになるんですよね、やり始めて。
主に、最近僕がこっちにいるからやれてないんだけど、頻繁によくやってたのが、HAPPY HIKERS BARって言って、福岡のあるレストランを借りて、そこにゲストスピーカーとして、自分たちのコミュニティの誰かに短いこんな山行ってきたよとか、こんなスキーしたよみたいな、そういうプレゼンテーションしてもらって、みんなでワイワイってするようなHAPPY HIKERS BARっていうのと、あとは、HAPPY HIKERSのウェブマガジンというのを毎月更新してて、いろんなコミュニティのみんなに執筆してもらって、それを毎月更新してるっていうのも、もうすぐ100号になります。あと、2年に1回開催しようということで、HAPPY HIKERSの法華院ギャザリング、法華院っていうのは、九州のど真ん中にくじゅうという山の連なりがあるんですけど、それのまたまたど真ん中に、昔からある温泉のある山小屋さんなんですけれども。
[江良]
温泉もある。
(2023年のHappy Hiker Gathering風景 / photo : 馬場祐吏)
[豊嶋]
温泉もあるんです。そこを会場にさせていただいて、そこに、みんなで集まろうよっていうギャザリングのイベントごとを2年に1回目標にして開催してきていて、一旦一回コロナ禍で中断してた時期があったんですけど、今年またそれをやることになってます。第4回目として。これは別にさっきで言う、稼ぐ仕事ではない側の、なんならコミュニティづくり、コミュニティ運営をしているよっていうだけのことなんだけど、そんな感じのものがハッピーハイカーズです。
[江良]
そのギャザリングのイベントが、今年は11月の?
[豊嶋]
11月29日土曜日に開催します。
[江良]
そこで飲み会の夜の時のチャリティーコーナーっていうのがあるんですよね?
[豊嶋]
懇親会ですね。食堂を使わせてもらってるんですけど、参加者が300人超えるぐらいのイベントなんですけど、その中で来たい人だけ集まるんですけど、懇親会ってもみんながお酒を勝手に持ってきて、飲んでみんなで交流してるんですけど、そこで毎回恒例のチャリティーオークションっていうのをやってて、ギア、インディブランドだったり、いろんな面白い道具作ってる人たちに、マルシェを昼間やってもらってるんですけど、そこの皆さんに協力してもらって、サンプル商品で売ってはないんだけど、今回はこれを出しますみたいなので、オークションに出品してもらってるんですよね、チャリティーとして。それを僕らのスタッフが、じゃあ次の商品はこれです!って言って、じゃあ1万円からスタート!って。お酒飲んでるから、はい、1万5000円!、1万8000円!みたいなのが、わーってなっていって、結構収益金になるんですけど、それをくじゅうの山の、いろんな登山道の整備だったりとか、そういったものに使っていただいてるっていう、そういうオークションをやってて、それのTシャツなんです。
[江良]
で、今年第4回目、そのイベントに、各年にテーマがあるんです。
[豊嶋]
はい。毎年、今回で4回なんですけれども、いつもテーマを設けています。第1回目は、まさにウルトラライトっていう言葉をテーマにして、ウルトラライトハイキングっていうものが、まだ九州でそこまでちゃんと紹介されてなかった時期だったので、みんなに知ってもらいたいなっていうのもあったのと、ウルトラライトハイキングとせずに、ウルトラライトで止めたのは、ウルトラライトハイキングって、ハイキングの方法論なんだけど、ウルトラライトライフぐらいまで応用可能な、さっき僕がお話したようなものでもあると思っているので、そこぐらいの幅でテーマ設定しました。
第2回がローカルなんですけれども、北海道から九州まで、日本全国いろんな山とか自然があって、そこに沿った形での、みんなアウトドアクティビティやってたりとか、過ごし方があったり文化があったりするから、各地から6人ぐらいゲスト来てもらって、北海道代表、東北代表、関西代表、四国代表みたいな感じで、で九州の人も入ってもらって、それぞれのお国自慢大会みたいなのをプレゼンテーションしてもらって、こんなに素晴らしい北海道は、とか。そこから見えてくるのは、どこも面白い、どこも素晴らしいという感じで。結局いろんなところに、どこにもいいところがあって、大事なのは、その自然とか、そこの文化と、どういう関係性を育めているかの方が大切だよね、みたいなことで、ローカルというテーマでいきました。
で、パンデミックを経て、第3回目がライフスタイルというのをテーマにしたんですけれども、それはカッコ書きで、生き方という意味でのライフスタイルというふうにしたんですけれども、だから、なんかもう本当に結構コロナ禍で、何かがあったら、世の中が一変しちゃうというふうに、我々全員が体験したと思うんですけど、そんな中で、それぞれはどういうふうに生きていくんだというのが、逆にすごい問われた時間だったなというふうに思ったので、それはハイカーも例外じゃないねということで、ライフスタイルというのを第3回にして。
で、第4回、今回はインタービーイングという、ちょっと聞き慣れない言葉かと思うんですけれども、これはベトナムの僧侶のティク・ナット・ハンという方の言葉なんですけど、インターという関係みたいなことを、ビーイングという存在という言葉で、彼が提唱した言葉なんですけど、日本語では、相互共存、相互に共存するという、全てのものが繋がっていて、そういう複雑系として、この世のものが全部あるよねというか、そういうふうなことを提唱していて、だから本来敵とか味方とかもないし、全部が循環して繋がっている存在なんですよということを、ティク・ナット・ハンさんは仏教の僧侶なので、仏教的な思想ではあると思うんですけれども、今本当にいろんなことが、社会状況とか戦争があったり、いろんな分断とか格差とか、気候変動とか、いろんなことがあって、全然良い方向に向かっている感じが全くないというような、ちょっと不安になるような時代ですけれども、僕たちもハイキングの時はそこから切り離されて楽しもうというのも、ちょっと楽観的すぎるなという気もするというか、ハイカーっていう目線を通して、そういうものと向き合っていったり、適応せざるを得ないことがあったり、改善していくことに気づいていけるような、そういうテーマを設定したい、インタービーイングが今年のテーマですね。
(Happy Hikers Hokkein Gathering 2025向けチャリティGrow OrganicTシャツ*イメージ画像)
[江良]
本当に繋がっているから、他の他人とかに見えることでも、自分ごとというか、どこかで自分と繋がっているし、そういう意識が生まれてこないと、今の社会の政治の状況って良くならないような気がしますよね。僕がやっているこのTシャツのことにしても、結局作っている人がいるわけで、綿を作る人、糸を作る人というのがいて、僕たちもそこに他人ごとではないというか、そういうことって僕もすごい思っているところで、豊嶋さんからインタービーイングっていう、聞き慣れない言葉を聞いた時にすごい良い言葉だなと思って、このインタービーイングをTシャツにポンとプリントして、チャリティーでやっていただいて、
[豊嶋]
チャリティーオークションで出品させていただく用として作っていただくので。
[江良]
登山道の整備とか。ベンチを今回作られるんですか?
[豊嶋]
去年の収益で、山の中に設置されて、ベンチが設置されていたのが、それ老朽化とかで撤去されたという話があったので、そこにもう一回、HAPPY HIKERSのチャリティーオークションからの寄贈という形で、ベンチを設置させてもらうことになったんですけど、そういった感じで、今回のチャリティーオークション、どうなるか分からないですけど、一部としてTシャツを出していただくというのを。なので、HAPPY HIKERSの法華院ギャザリングに来た人は、現金いっぱい持ってきてくださいね!みたいな。カードはオークションでは使えませんので。
[江良]
分かりました。HAPPY HIKERSのウェブも見ていただくと、イベントの参加の仕方とかも分かると思うので、ホームページにもリンク貼らせてもらえればと思います。長い時間になりましたけれども、今日は本当にお家にお招きいただいて、本当にありがとうございました。
[豊嶋]
いつでも遊びに来てください。そして、作業を手伝っていただいて。
[江良]
でもやっぱり、デッキの木材の防腐剤みたいなものを塗って、普段そういうふうにDIYして、何かそれが家とか、誰かの生活の一部になっていくって、東京だとなかなかないというか、本当にないと思うのではなかなか。だから、そういう作業に、仕事に参加できる喜びというか、そういったものを逆に感じられて良かったなと思っています。また、完成したところを遊びに来たいと思います。本日のゲストは豊嶋秀樹さんでした。どうもありがとうございました。
[豊嶋]
ありがとうございました。